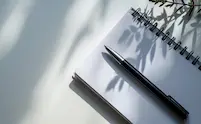1000円の着服で退職金1200万円が全額不支給に!? 最新最高裁判例から学ぶ、懲戒解雇と退職金のリアル

社労士 鈴木 貴雄
東京都社会保険労務士会
この記事の執筆者:社労士 鈴木 貴雄
区役所と民間、官民双方の豊富な現場経験を強みに、複雑な法改正、助成金活用、労務トラブルまでスピーディーに解決します。机上の空論ではない、実績豊富な社労士として貴社の状況に即した実践的なサポートで事業の成長を力強く後押しするパートナーです。
目次
はじめに
令和7年4月18日、公務員の退職手当に関する衝撃的な最高裁判例が出されました。
地方公共団体が経営するバスの運転手が、運賃1000円を着服したことなどを理由に懲戒免職となり、それに伴い約1211万円の退職手当が全額不支給とされた事案です。最高裁は、この全額不支給処分を「適法」と判断しました。
着服額が1000円と比較的少額であるにもかかわらず、高額な退職金の全額不支給が認められたこの判例は、大きなインパクトを与えました。
「これは公務員の話だから、民間企業には関係ない」と思われるかもしれません。しかし、そう判断するのは早計です。
本記事では、この最新判例のポイントを分かりやすく解説するとともに、民間企業における懲戒解雇と退職金不支給の実務上の留意点について、企業の皆さまが今すぐ備えるべきことを整理します。
1.どんな事件だったのか?(事案の概要)
まず、今回の最高裁判例の事案を整理します。
- 当事者(原告):京都市交通局に約29年間勤務していたバスの運転手
- 非違行為(問題となった行動):
- 乗客から受け取った運賃1,000円を運賃箱に入れずに着服した。
- 乗客がいないバス車内で、勤務中に複数回(週に5回程度)電子タバコを使用した。
- 会社の処分:上記の行為を理由に懲戒免職処分。あわせて、京都市の退職手当支給規程に基づき、退職手当(約1211万円)の全額を支給しないとする処分(全部支給制限処分)を行った。
- 裁判の争点:この「退職手当の全額不支給処分」が重すぎて違法ではないか。
原告の職員は、この全額不支給処分の取り消しを求めて、京都市を相手に訴訟を提起しました。
2.最高裁はどのように判断したか?(判旨のポイント)
結論:退職金の全額不支給は「適法」
最高裁は、退職手当の全額不支給処分は適法であり、職員の請求には理由がないと判断しました。
判断の枠組み:「裁量権の逸脱・濫用」はあったか?
裁判所は、退職手当を支給するかどうか、また、どの程度支給しないかという判断は、基本的に処分を行う者(本件では京都市の管理者)の裁量に委ねられるとしました。
ただし、その裁量判断が社会通念上、著しく妥当性を欠き、**「裁量権の逸脱・濫用」**にあたる場合は、その処分は違法となります。
今回の裁判では、この「裁量権の逸脱・濫用」があったかどうかが最大のポイントとなりました。最高裁は、以下の要素を比較検討しています。
【処分が重すぎるといえる事情(裁量権の逸脱・濫用を肯定する方向)】
- 着服行為による金銭的損害は1,000円と少額であり、被害弁償も行われていること。
- 職員が約29年という長期間にわたり勤続し、本件を除いて懲戒処分を受けた経歴がなかったこと。
【処分はやむを得ないといえる事情(裁量権の逸脱・濫用を否定する方向)】
- 公務の遂行中に公金を着服するという行為自体の悪質性が極めて高いこと。
- バスの運転手には運賃の適正な取扱いが強く求められ、着服行為は事業に対する市民の信頼を大きく損なうものであること。
- 勤務中に週5回も電子タバコを使用していたことは、勤務状況が良好でなかったことを示していること。
- 非違行為が発覚した後、当初は着服を否認するなど、調査に対する態度が不誠実であったこと。
最高裁は、これらの事情を総合的に考慮した結果、「処分が重すぎるといえる事情」を認めつつも、「処分はやむを得ないといえる事情」をより重く評価し、本件の全額不支給処分は裁量権の逸脱・濫用にはあたらない、と結論付けました。
【補足】なぜ公務員には厳しい判断がなされやすいのか?過去の判例でも、公務員の退職手当については、その職務の公共性や、公務全体に対する国民の信頼に与える影響が重視される傾向にあります。そのため、非違行為が公務への信頼を著しく損なうものである場合、退職金の不支給は原則として適法とされ、例外的に処分が重すぎる場合にのみ違法と判断されます。
3.この判例、民間企業にも影響は?
では、この判例は民間企業にどのような影響を与えるのでしょうか。
民間企業における退職金の不支給については、過去の「みずほ銀行事件」判例で重要な考え方が示されています。
【民間企業における退職金不支給の考え方】
- 原則として、就業規則等に定めがあれば不支給は適法。ただし、その判断が権利の濫用にあたる場合は違法となる。
- 退職金全額を不支給とするためには、**「永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」**があったことが必要。
今回の最高裁判例も、着服行為が「事業に対する信頼を大きく損なう」点を重視しています。これは、民間企業における「重大な不信行為」の判断と通じるものがあります。特に、銀行業や警備業など、高いレベルの信頼性や廉潔性が求められる業種では、たとえ少額であっても、横領や着服は「永年の功労を抹消するほどの重大な不信行為」と判断される可能性が十分にあります。
4.企業が今すぐ備えるべきこと ~就業規則の重要性~
今回の判例から企業が学ぶべき最も重要なことは、退職金に関する規程をきちんと整備しておくことです。特に、不支給条項の設計が、いざという時に会社を守る鍵となります。
弊所(カインド社労士事務所)で推奨している条項例をご紹介します。
【退職金規程(不支給条項)の条文例】
第◯条(不支給・返還)1.就業規則第◯条(懲戒解雇)の定めに基づき懲戒解雇された者、または懲戒解雇事由に該当する行為を行った者には、退職金を支給しない。ただし、情状により、退職金の一部を減額して支給することがある。2.使用者は、退職金を支給した後に、当該労働者の在職期間中に懲戒解雇事由に該当する事実があったことが判明した場合、支給した退職金の全部または一部の返還を求めることができる。
この条文のポイントは以下の2点です。
- ポイント①:「懲戒解雇事由に該当する行為を行った者」も対象とする
→ これにより、問題が発覚した際に、会社からの懲戒解雇を免れるために先手を打って退職届を提出した従業員に対しても、退職金を不支給とすることが可能になります。 - ポイント②:退職金支払い後の「返還請求」を明記する
→ 退職後に不正が発覚した場合でも、支払った退職金の返還を求める法的根拠となります。
就業規則や退職金規程は、平時にはあまり意識されないかもしれませんが、こうした不測の事態に会社を守るための重要な「盾」となるのです。
最後に:貴社の就業規則は、万全ですか?
今回の最高裁判例が示す最も重要な教訓は、懲戒処分やそれに伴う退職金の不支給といった重大な判断を下す際、その最終的な拠り所となるのは「就業規則」であるという厳然たる事実にあります。
企業の「想い」や「当然の理屈」だけでは、法的な紛争において会社を守ることはできません。裁判所が判断の基準とするのは、あくまで客観的なルール、すなわち就業規則の具体的な条文なのです。
曖昧な規定や、長年見直されていない古い就業規則では、いざという時に会社を守る「盾」としての役割を十分に果たせない可能性があります。
就業規則の整備は、企業の健全な発展を支える基盤であり、最重要のリスクマネジメントの一つです。
貴社の規程が最新の判例動向を踏まえ、実態に即した内容となっているか、この機会に一度ご確認されてはいかがでしょうか。
就業規則の見直しや強化についてご検討の際は、ぜひ専門家であるカインド社労士事務所までご相談ください。